release:
update:
release:
update:

「WEBサイトのデザインを刷新したいけど、どのツールを使えばいいんだろう?」
「社内で簡単なバナーや資料を作りたいけれど、デザイン経験者がいない」
もしあなたが今、このようなお悩みをお持ちなら、この記事がきっとお役に立ちます。
ビジネスにおいて、デザインの重要性はますます高まっています。
これら顧客とのあらゆる接点でデザインは「企業の顔」となるものであり、ブランドイメージを左右します。
しかし、デザインと聞くと、「専門的なスキルが必要なのでは?」と尻込みしてしまう方もいるかもしれません。また、いざデザインに取り組もうと思っても、世の中には非常に多くのデザインツールが存在し、どれを選べば良いのか迷ってしまう場合もあるでしょう。
そこで今回は、2025年最新版として、ビジネスシーンで活用できるおすすめのデザインツールを10種類厳選してご紹介します。それぞれのツールの特徴や得意分野を比較しながら、あなたの会社の目的やスキルレベルに合った最適なツールを見つけるための選び方ガイドになっていますので、ぜひ最後まで読み、貴社のビジネスを加速させるデザインツールを見つけてください。
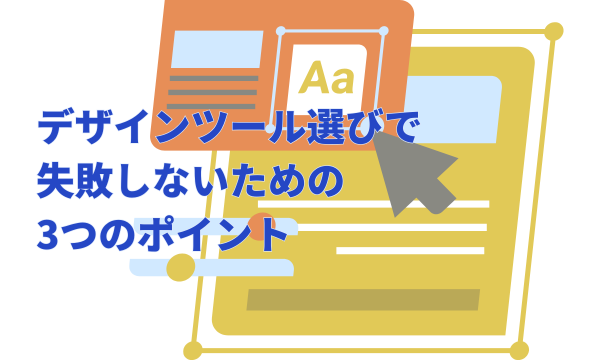
具体的なツールを見ていく前に、まずは自社に合ったデザインツールを選ぶために押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
「何のためにデザインツールを使うのか?」は最も重要なポイントです。
目的によって最適なツールは全く異なります。まずは、デザインを通じて何を達成したいのかを社内で明確にしましょう。
誰がデザインツールを使うのかも、選び方の大切な要素です。
専門的な知識やスキルが必要なツールもあれば、初心者でも直感的に操作できるツールもあります。ツールの習得コストも考慮し、利用する人たちが無理なく使いこなせるものを選ぶことが、継続的な運用に繋がります。
多くのデザインツールには、無料プランと有料プランがあります。月額費用や年額費用、機能制限などを事前に確認しましょう。
また、チームでデザイン作業を進める場合は、共同編集機能やクラウドでのデータ共有機能が充実しているかどうかも重要なポイントです。リアルタイムで複数人が同時に作業できるツールは、プロジェクトの効率を大きく向上させます。デザインをする場面を想定して、どのような規模で、どのような形で「連携」できるツールを選び必要があるかを検討しましょう。
これらのポイントを踏まえて、次からおすすめのデザインツールを見ていきましょう。

ここでは、用途やスキルレベル別に幅広いデザインツールをご紹介します。(表示の価格は2025年7月末日現在のものです)
UI/UXデザインのデファクトスタンダードとも言えるWEBベースのデザインツールです。リアルタイム共同編集機能が非常に強力で、複数人でのデザイン作業やフィードバックのやり取りがスムーズに行えます。プロトタイプ作成機能も充実しており、完成イメージを共有しやすい点が魅力です。
Adobe社が提供するUI/UXデザイン・プロトタイピングツールです。PhotoshopやIllustratorなど他のAdobe製品との連携が非常にスムーズなため、既にAdobe Creative Cloudを利用している企業にとっては導入しやすいでしょう。
画像加工・編集のプロフェッショナルツールとして、WEBデザイン、グラフィックデザイン、写真編集などあらゆる分野で利用されているツールです。WEBサイトのキービジュアルやバナー、アイコンなどの素材作成に必須のツールと言えるでしょう。2025年現在、AI機能「Adobe Firefly」との連携も進み、より高度な画像生成や編集が可能になっています。
ロゴ、アイコン、イラスト、図形などのベクターグラフィック作成に特化したツールです。ベクター形式(点とそれらを結ぶ線・曲線などの数学的な座標情報で画像を表現する方式)のため、拡大・縮小しても画質が劣化しない点が最大のメリット。企業のロゴマークや販促物のデザイン、WEBサイトのアイコン作成など、多岐にわたる用途で利用されています。
Macユーザーに根強い人気を持つUI/UXデザインツールです。プラグインの豊富さや軽快な動作が特徴で、シンプルで直感的なインターフェースが評価されています。FigmaやXDと比較されることが多いツールですが、Mac環境での作業効率を重視するデザイナーに選ばれています。
デザインの専門知識がない方でも、豊富なテンプレートと直感的な操作でプロ並みのデザインを作成できるWEBベースのツールです。SNS投稿画像、プレゼン資料、チラシ、ポスターなど、多岐にわたるデザインに対応しており、ビジネスシーンで非常に活用されています。AI機能も充実しており、テキストからの画像生成なども可能です。
Microsoftが提供するAIを搭載したデザインツールです。テキストを入力するだけで画像を生成したり、既存のデザインにAIが最適なレイアウトやフォントを提案したりするなど、AIがデザイン作業を強力にアシストしてくれます。Microsoft 365との連携も期待されます。
コーディングの知識がなくても、デザインツール感覚でWEBサイトを自由にデザイン・公開できるノーコードWEBサイト制作ツールです。直感的なドラッグ&ドロップ操作で、レスポンシブデザインにも対応した高品質なサイトを構築できます。
テキストから非常に高品質で芸術性の高い画像を生成できるAIツールです。WEBサイトのキービジュアル、ブログ記事のアイキャッチ、広告クリエイティブのアイデア出しなど、オリジナリティのあるビジュアルが必要な場合に活用できます。
OpenAIが開発した画像生成AIで、ChatGPT-4Vと連携して利用できる点が大きな特徴です。より自然なテキスト指示で、具体的なシーンやオブジェクトを含む画像を生成する能力に優れています。生成した画像をChatGPTでさらに編集したり、文章と合わせて活用したりすることも可能です。

ご紹介した10種類のツールの中から、あなたの会社に最適なものを選ぶための具体的なステップをご紹介します。これは、単に機能比較をするだけでは見えてこない、貴社のビジネスに本当の意味で貢献するツールを見つけるためのプロセスです。
まず、貴社が現在抱えているデザインに関する具体的な課題と、それを解決するために何を達成したいのかを詳細に書き出してみましょう。「デザインを良くしたい」など漠然とした目標ではなく、より具体的な成果をイメージすることが重要です。成果のイメージができたら、それがツールを選ぶ基準となります。
例えば、「WEBサイトの更新に時間がかかっている」と感じているなら、「デザイン変更やコンテンツ追加を、外部委託せず社内でスピーディーに完結できるようにしたい」など「内製化によるスピード向上」が目的となるでしょう。その場合、ノーコードやローコードでWEBサイトを構築・管理できるツールが有力な選択肢となります。
また、「SNS投稿のエンゲージメントが低い」ことが課題であれば、「視覚的に魅力的で、ターゲット層の目を引く高品質な画像や動画を効率的に制作し、エンゲージメント率を向上させたい」という目的が見えてきます。この場合、SNS投稿に特化したテンプレートが豊富で、直感的に操作できるツールが適しているかもしれません。
「デザイナーがおらず、デザインの外注コストが高い」という課題には、「専門知識がなくても、ブランドガイドラインに沿った基本的なデザインを社内で完結できる体制を作り、外注コストを削減したい」という目的が考えられます。このケースでは、テンプレートが豊富で学習コストの低いツールが理想的です。
このように、具体的な課題を深掘りし、その解決によって得られる「理想の状態」を明確にすることで、必要なツールの方向性が定まります。
候補となるツールをいくつか絞り込めたら、実際にそれらを触ってみることが何よりも重要です。多くのデザインツールには、機能制限のあるものの無料プランや、期間限定の無料トライアルが用意されています。そうしたサービスを最大限に活用して、カタログスペックだけではわからない操作性や、実際のワークフローへの適合性を確認しましょう。
無料トライアルを有効に活用するためのポイントは、主に次のとおりです。
この実践的な試用期間を通じて、実際に導入した際のイメージを具体化し、失敗のリスクを低減することができます。
現在のデザインニーズだけでなく、将来的にデザインの範囲を広げたい、あるいはチームのスキルアップに合わせてより高度な表現に挑戦していきたいといった展望がある場合は、そのツールの「拡張性」も考慮に入れるべきです。
注目すべき拡張性は、主に次のようなものです。
目先の課題解決だけでなく、将来の成長を見据えた選択をすることで、デザインツールへの投資を最大限に活かすことができるでしょう。
デザインツールは、単なる「絵を描く道具」ではありません。企業のブランディングを強化し、顧客とのコミュニケーションを深め、最終的にビジネスの成長を加速させるための強力な武器となります。
今回紹介した10種類のツールは、それぞれ得意分野や特徴が異なります。ぜひこの記事を参考に、貴社の目的やスキルレベルに合った最適なデザインツールを見つけてみてください。
もし「どのツールが良いか迷う」「WEBサイトのデザインを最初からプロに任せたい」とお考えでしたら、株式会社MUにお気軽にご相談ください。貴社の課題や目標に合わせた最適なWEBサイト制作・デザイン支援をご提案させていただきます。
弊社にご関心をお持ちいただき、
ありがとうございます。
DX推進をはじめ、Web制作等の
お見積り、サービスに関する
ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ内容の確認後、
担当者よりご連絡致します。
release:
update:
release:
update:
release:
release:
update:
release:
update:
release: