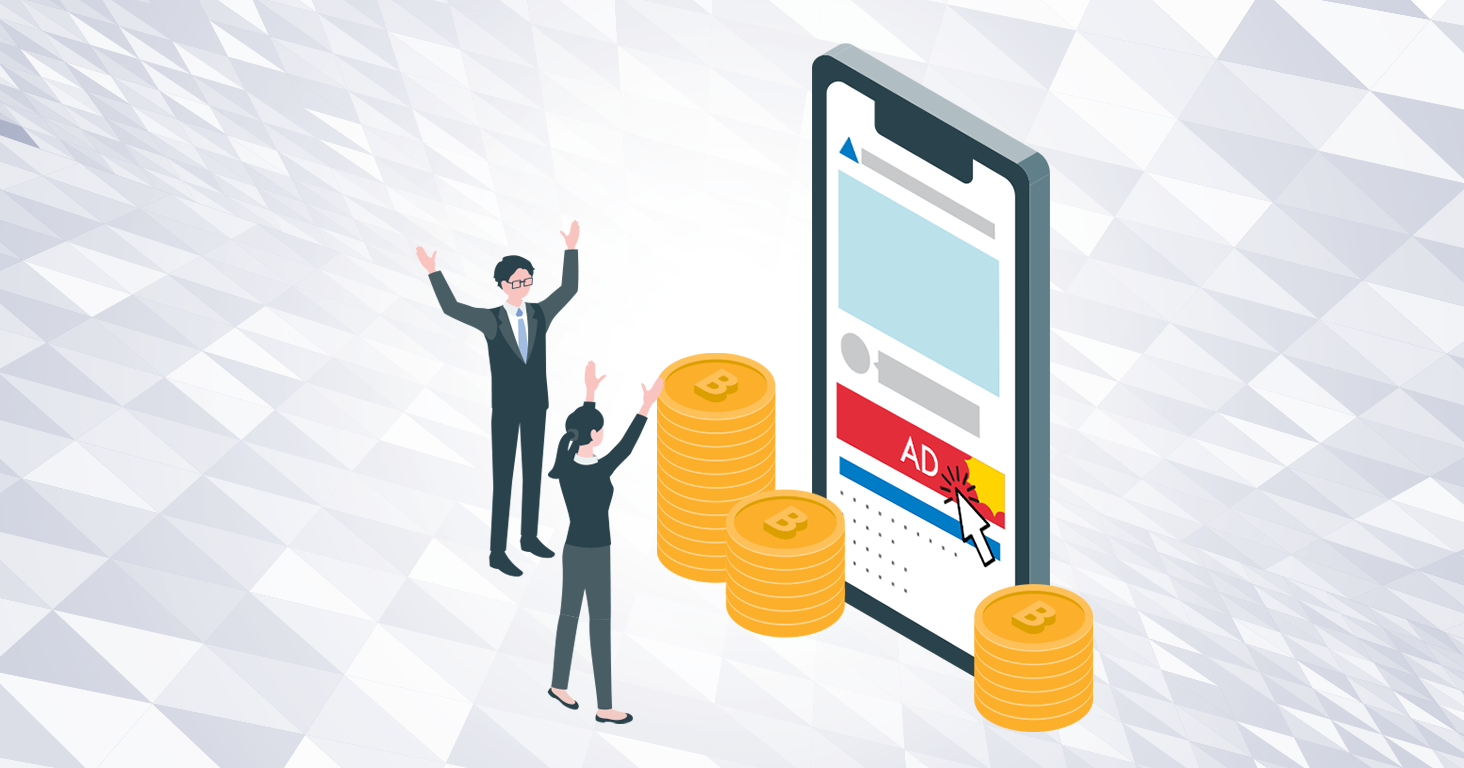release:
※本Blog DX記事の最新・詳細版は、DX専門メディア『DXportal』にて公開しています。
「DX推進」という言葉が普及するとともに、「システム内製化」も大きな注目を集めています。経営者や担当者の中には「うちもシステム開発を内製化すべきなのだろうか?」とお考えの方もいるかもしれません。
確かに、自社でシステムを開発する内製化は、ビジネスのスピードアップやコスト削減に繋がる可能性を秘めています。しかし、「内製化さえすれば全て解決する」という単純なものではありません。むしろ、安易な内製化は、かえって企業に大きな負担とリスクをもたらす可能性もゼロではないのです。
この記事では、システム内製化が注目される背景から、そのメリット・デメリット、そして貴社が内製化に向いているのかどうかを見極めるための具体的なチェックポイントまで、徹底的に解説します。
内製化が貴社にもたらす「光」と「影」を正しく理解し、後悔しない意思決定をするための参考にしていただければ幸いです。
目次
- なぜ今、システム内製化が注目されるのか?その背景とメリット
- 市場の変化とビジネススピードの加速
- 技術の進化と開発ツールの多様化
- 内製化が企業にもたらす具体的なメリット
- 内製化の落とし穴!知っておくべきデメリットや課題
- 人材確保・育成の困難さ
- 初期投資と期間
- 属人化のリスク
- 品質担保の難しさ
- 保守・運用の負担増
- 変化する技術トレンドを追い続ける負担
- 内製化の適正を見極める5つのチェックポイント
- ポイント1. 必要なリソース(人材・予算)は確保できるか?
- ポイント2. 経営層のコミットメントは高いか?
- ポイント3. 開発したいシステムの特性は?
- ポイント4. 社内に技術的な知見を持つ人材はいるか?
- ポイント5. 長期的な視点で事業戦略と紐づけられるか?
- まとめ:内製化は「目的」ではなく「手段」である
なぜ今、システム内製化が注目されるのか?その背景とメリット

従来のシステム開発では、専門のベンダーに開発を任せるのが一般的でした。しかし、現在では内製化の動きが加速しています。つまり、社内のリソースだけで、システムを開発することが主流になってきているのです。その背景には、市場の変化と技術の進化が大きく関係していると言ってよいでしょう。
本章では、システム内製化が注目を集める理由と、そのメリットを確認します。
市場の変化とビジネススピードの加速
現代のビジネス環境は、目まぐるしく変化しています。競合との差別化を図り、顧客ニーズに迅速に対応するためには、ビジネス戦略とシステムを密接に連携させ、常に改善し続けなければなりません。
外部ベンダーに開発を依頼すると、どうしても要件定義や開発、テスト、修正といった各フェーズに時間と手間がかかり、変化への対応が遅れてしまうケースがあります。システムを内製化すれば、このベンダーとのやり取りにかかるタイムラグがなしで、迅速に対応することができるのです。
技術の進化と開発ツールの多様化
近年、ローコード開発やノーコード開発といった、専門知識がなくてもシステム開発を可能にするツールが次々に登場しています。また、クラウドサービスの普及により、サーバーなどのインフラ構築の手間も大幅に削減できるようになりました。これにより、以前に比べてシステム内製化のハードルが格段に下がったと言えるでしょう。
内製化が企業にもたらす具体的なメリット
内製化がもたらす具体的なメリットは多岐にわたります。
- コスト削減: 外部委託にかかる費用や、その都度発生する見積もり・契約の手間を省くことで、トータルコストの削減に繋がる可能性がある
- ノウハウ蓄積と技術資産化: システム開発を通じて得られた技術的なノウハウは、企業の貴重な技術資産となり、将来的なシステム改修や新規開発において、外部に依存せず自力で対応できる基盤が築ける
- 柔軟な対応と迅速な改善: 外部ベンダーとの調整や依頼が不要な分、開発サイクルを短縮しるためビジネスの状況や市場の動向に合わせて、システムをスピーディに改善できるようになる
- 事業戦略との密接な連携: 開発部門が事業部門と同じ社内にいることで、ビジネスの目標や現場の課題をより深く理解してシステムを構築できるため、本当に必要とされているシステムを作りやすくなる
- 属人化の解消(外部ベンダー依存からの脱却): 特定の外部ベンダーにシステムの維持・管理を任せきりにすることで発生する「ベンダーロックイン」のリスクを回避でき、より柔軟な運用が可能になる
内製化の落とし穴!知っておくべきデメリットや課題
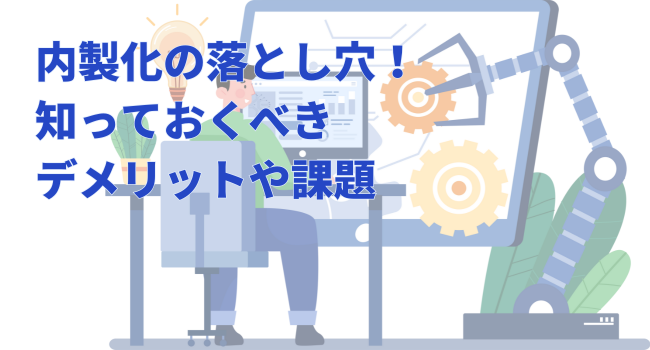
内製化には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットや課題、潜在的なリスクも存在します。これらの「影」の部分を理解せずに進めると、かえって大きな損失を招くことになりかねません。
人材確保・育成の困難さ
システム開発に必要なスキルを持つ優秀なエンジニアの確保は、非常に競争が激しいのが現状です。採用できたとしても、彼らを社内に定着させるための環境整備や、継続的なスキルアップのための教育コストも必要になります。未経験者を育成するとなると、時間も費用もかかるのは難点です。
初期投資と期間
内製化には、開発環境の構築、必要なソフトウェアライセンスの購入、開発ツールの導入といった初期投資が必ず発生します。いくら開発ツールが充実化し、クラウドなどのリソースむ活用しやすくなったとはいえ、ある程度の費用は必要です。
また、実際にシステムが稼働し、効果を実感できるようになるまでには、期間を要するため、その間のランニングコストが余計に発生することも覚悟しなければなりません。
属人化のリスク
特定の外部ベンダーの依存状態から脱却したとしても、システムに関する知識やノウハウが社内の特定のエンジニアに集中してしまっては本末転倒です。その人が退職すると、たちまちシステムが「ブラックボックス」化してしまうリスクがあります。
品質担保の難しさ
専門的な知識や経験が不足していると、開発したシステムの品質が低下する恐れがあります。バグの多発、動作の不安定さ、そして最も危険なのがセキュリティリスクです。専門的な知見がないまま開発を進めると、脆弱性のあるシステムを構築してしまう可能性が出てきてしまうのです。
保守・運用の負担増
システムは開発して終わりではありません。稼働後の運用・保守も非常に重要です。予期せぬトラブル対応、サーバーの監視、機能追加や改修など、継続的な手間とコストが発生します。これらの作業を全て社内で負担しなければならないとなると、本来の業務に支障をきたす可能性もあります。
変化する技術トレンドを追い続ける負担
IT技術は日進月歩で進化しています。常に最新の技術やトレンドをキャッチアップし、それをシステムに反映させていくには、継続的な学習と研究が必要です。この負担が、社内のリソースを圧迫するケースも考えられます。
内製化の適正を見極める5つのチェックポイント

内製化の「光」と「影」を理解した上で、貴社が内製化に本当に向いているのか、それとも外部委託を続けるべきなのかを判断するために、以下5つのチェックポイントを確認してみましょう。
ポイント1. 必要なリソース(人材・予算)は確保できるか?
システム内製化は、決して片手間でできるものではありません。専門的な知識を持つエンジニアの採用・育成、そして開発環境を整えるための十分な予算が確保できるかどうかが最初の大きな壁となります。現時点で具体的な計画がないのであれば、内製化は慎重に検討すべきでしょう。
ポイント2. 経営層のコミットメントは高いか?
内製化は、単なるIT部門だけの問題ではありません。全社的な取り組みとして、経営層が強いリーダーシップを発揮し、必要な投資や組織改編を後押しする姿勢が不可欠です。トップダウンでの推進力がなければ、途中で頓挫してしまう可能性が高まります。
ポイント3. 開発したいシステムの特性は?
貴社が内製化したいと考えているシステムは、どのような特性を持っていますか?
独自性が非常に強いシステムで、他社にはない競争優位性を生み出すものや、ビジネスの変化に合わせて継続的に機能改善が必要なものか?、それとも、汎用的な機能が多く、市販のパッケージソフトやクラウドSaaSで十分対応できるものなのか?
独自性が高く、継続的な改善が求められるシステムほど、内製化のメリットは大きくなります。逆に汎用的なシステムであれば、既存のサービスを利用する方が効率的かもしれません。
ポイント4. 社内に技術的な知見を持つ人材はいるか?
システム開発をゼロから完全に自社だけで始めるのは、非常にハードルが高いものです。プロのエンジニアが一人もいない状態で内製化を進めようとすると、プロジェクトの立ち上げから運用まで、予期せぬ困難に直面する可能性が大きくなってしまうでしょう。
例えば、
- 現状の課題や要件を正確に言語化し、開発計画を立てる
- 最適な技術スタックやツールを選定する
- セキュリティや運用保守について考慮する
こうした初期段階の作業でさえ、専門的な知識がなければ正しい判断が難しくなります。そのため、内製化をスムーズにスタートさせるには、基本的な知識や経験を持つ人材が社内に一人でもいるかどうかも、重要なチェックポイントの一つです。
知識や経験を豊富に持った人材が社内にいない場合は、まずは外部のパートナー企業に技術顧問として参画してもらう、あるいは技術力の高いフリーランスにスポットで手伝ってもらうなど、外部の知見を一時的に借りながら、社内メンバーが徐々にスキルを習得していくという段階的なアプローチを検討してみましょう。いきなりすべてを内製化するのではなく、まずは一部のプロジェクトや機能から内製化を始め、徐々にノウハウを蓄積していくという方法でも構わないのです。
ポイント5. 長期的な視点で事業戦略と紐づけられるか?
システム内製化は、単にコストを削減するためだけの「手段」ではありません。それが自社の中長期的な事業戦略とどのように結びつき、企業の成長に貢献するのかを明確に描けているでしょうか?内製化が、新たなビジネスチャンスの創出や、競争優位性の確立といった具体的な目標に繋がっていることが重要です。
逆に、そのようなビジョンが描けていないのであれば、一足飛びに内製化に移行するのではなく、まずは長期的な事業戦略の議論を重ねていった方が堅実です。
まとめ:内製化は「目的」ではなく「手段」である
システム内製化は、多くの企業にとって大きな可能性を秘めた戦略です。しかし、その「光」と「影」を正しく理解し、自社のリソースや状況、そして目指すゴールを明確にした上で、最適なアプローチを選択することが何よりも重要となります。内製化はあくまでビジネスを成長させるための「手段」であり、それ自体が「目的」ではないのです。
もし、貴社が内製化の適性診断で不安を感じたり、部分的に外部の専門家の力を借りたいとお考えでしたら、ぜひ一度株式会社MUにご相談ください。私たちは、お客様の現在の状況や目指すゴールを丁寧にヒアリングし、内製化の可能性を探るお手伝いや、最適なシステム開発戦略の立案、そして必要に応じた技術支援まで、お客様に寄り添ったサポートを提供しています。
貴社のビジネス成長に貢献する最適なシステム開発戦略を、私たちMUと一緒に考えていきませんか?