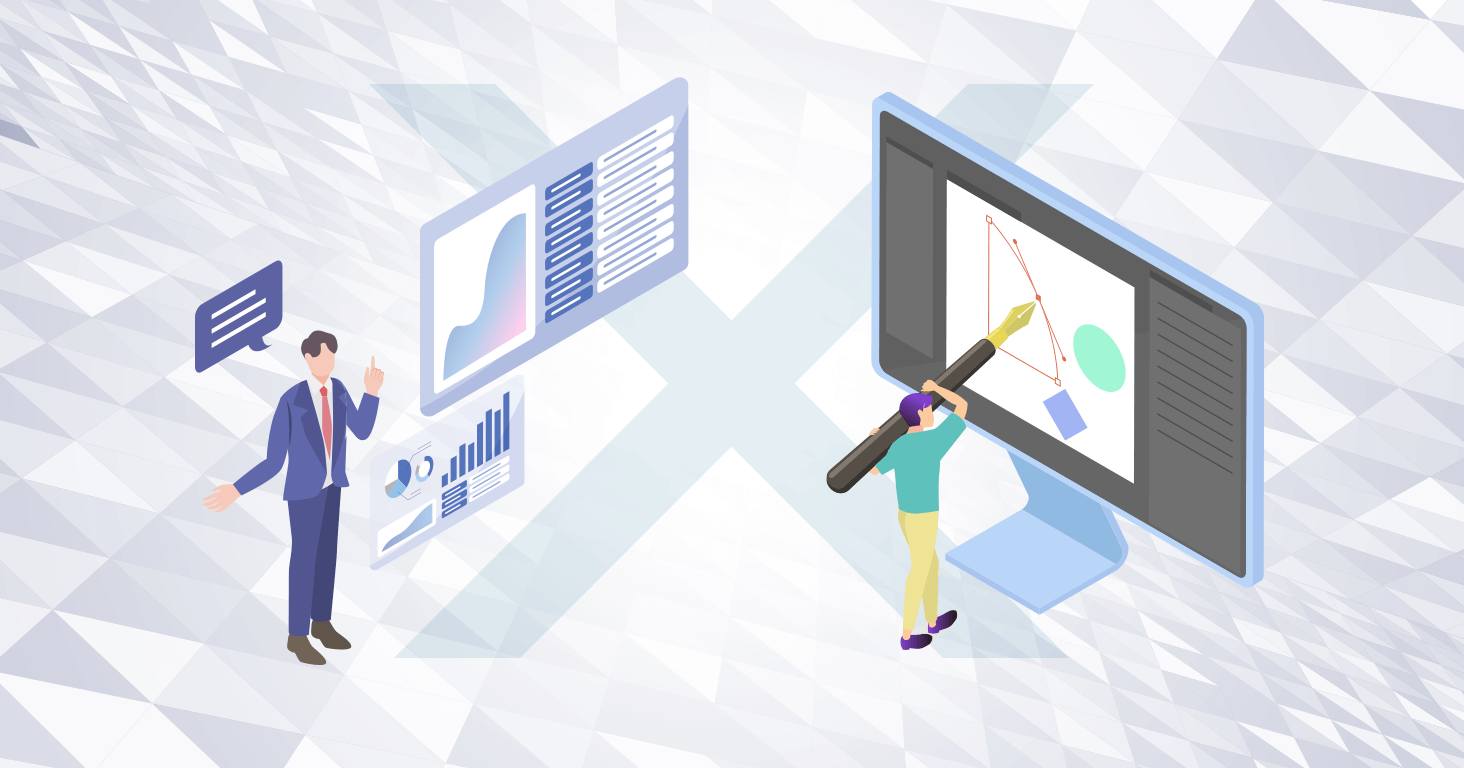release:
最近、Google検索の結果画面が変化したと感じませんか?
2025年9月9日、日本国内でGoogleの「AIモード」が正式に提供開始され、検索の仕組みが大きく変わりました。
特に注目すべきは、ユーザーの質問に対して、AIが要約した回答を表示する「AI Overviews」という機能です。これにより、ユーザーはWEBサイトをクリックしなくても必要な情報を得られる(ゼロクリック検索)ようになりました。ユーザーにとっては検索体験の向上につながることが期待される一方、サイトを運営する企業にとってはブログなどへのアクセス数が減ってしまうのではないかと懸念されています。
しかし、この変化は必ずしもネガティブなものではなく、オウンドメディアのあり方を見つめ直す絶好の機会でもあるのです。そこでこの記事では、AIモード時代を勝ち抜くために、今後WEBサイトを運営する上で必要となる4つのことを解説します。
目次
- その1:E-E-A-TがAIに選ばれる「一次情報」を左右する
- Experience(経験)に基づく「生きた情報」を伝える
- Expertise(専門性)を示すために「独自の分析・考察」を深掘りする
- Authoritativeness(権威性)を高めために「論拠」を明示する
- Trustworthiness(信頼性)を担保するために「透明性」を確保する
- その2:AIに「引用される」コンテンツ構造を意識する
- 簡潔なQ&A形式で「明確な答え」を冒頭に示す
- 構造化データ(スキーママークアップ)で「コンテンツの意図」を伝える
- 箇条書きやリスト形式で「視覚的なわかりやすさ」を高める
- その3:Google検索だけに頼らずに集客チャネルを増やす
- 指名検索(ブランド検索)を戦略的に促進する
- コンテンツを多角展開し「脱Google依存」チャネルを築く
- その4:企業ブログの成果を測るための新しいKPIを設定する
- AIによる概要への「引用・言及数」を追跡する
- 「ブランド名での検索回数」を認知度向上の証拠とする
- Google検索以外での「共感・行動の指標」を重視する
- まとめ:AI時代は「本質」が問われるチャンス
その1:E-E-A-TがAIに選ばれる「一次情報」を左右する
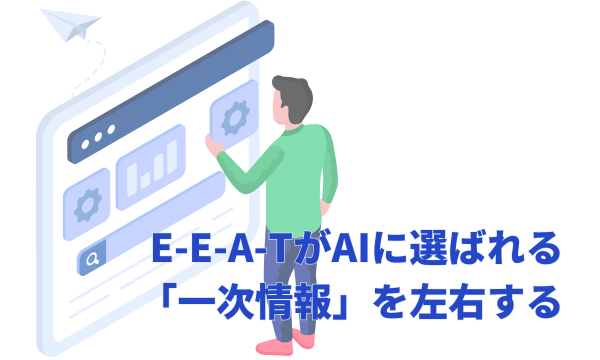
AIモードの中心機能である「AI Overviews」は、複数のWEBサイトから情報を集めて回答を生成します。つまり、AIに「引用する価値がある」と判断されるような、質の高いコンテンツの重要性がこれまで以上に高まります。また、AIが作成する概要で関心を持ったユーザーが「もっと詳しく知りたい」と思ってサイトを訪問してくれるような専門性や独自性も求められます。
逆に、他のサイトにもあるような一般的な情報をまとめただけのコンテンツは、そもそもAI Overviewで引用されにくく、もし引用されたとしてもAIの要約だけでユーザーは満足してしまい、サイトを訪れる理由がなくなってしまいます。AIがすぐに回答を生成できるような簡単な説明をしているだけのコンテンツの場合は、アクセス数が減少する可能性が高いでしょう。
では、AI時代に評価されるコンテンツとは、どのようなものでしょうか?
それは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を徹底的に追求した、そのサイトにしかない一次情報を豊富に含んだコンテンツです。AIはあくまで既存の情報を編集・要約するツールです。だからこそ、AIがまだ知らない、あるいはAIには生み出せない「生きた情報」を提供することで、コンテンツの価値は飛躍的に高まるのです。
Experience(経験)に基づく「生きた情報」を伝える
WEBサイトの評価に用いられるE-E-A-Tのなかでも、新しく追加された要素である経験(Experience)は、AIが最も真似できない領域です。抽象的な解説ではなく、「あなたが実際にやってみた結果」や「あなたの会社がお客様と歩んだ道のり」を具体的に示しましょう。
同様に、自社のサービスを導入した顧客の生の声や、具体的な課題解決のプロセスを詳細に解説した記事は、他の誰にも真似できない経験の塊です。導入事例を紹介する際も単に成功事例のアピールをするのではなく、「なぜその解決策を選んだのか」「どのような苦労や変化があったのか」といった個別具体的なストーリーを盛り込むことで、読者の共感を呼び、信頼性が高まります。
また、自社がWEBサイト制作で培ってきた「中小企業が失敗しないための企画書の書き方」のように、具体的な業務経験に基づいた独自のノウハウは、あなたのサイトの独自性になります。
Expertise(専門性)を示すために「独自の分析・考察」を深掘りする
多くの読者の方が実感している通り、日常のちょっとした疑問を解決するだけであればAIの要約で十分です。つまり、少し調べるだけで誰にでもわかるような内容を自社サイトで取り上げる意味はほとんどありません。様々な情報へのアクセスが容易になった現代において、「専門性がある」と見なされるためのハードルは上がっていると言えるでしょう。
逆に、特定のテーマに絞って、深く掘り下げた情報を提供することで、サイトの専門性が高めることができます。一般的な解説に終始するのではなく、「なぜそうなるのか」「どうするべきなのか」という独自の分析や考察を加えることが重要です。
例えば、業界の動向を独自に調査し、そのデータを分析した記事は、その分野における専門性を示す強力な証拠となります。すでに公表されているデータだけでなく、自社顧客の動向やアンケート結果などを統計的に分析し、「自社独自の視点」を提供することで他社との差別化が図れます。こうしたコンテンツを発信することで、AI時代においても、AIには代替不可能な専門性を有するWEBサイトとして評価され続けることができるでしょう。
Authoritativeness(権威性)を高めために「論拠」を明示する
権威性とは、「このサイトが掲載しているなら信じられる」「この人の意見を参考にしたい」という信頼の証です。権利性の裏付けとなるのが、「誰がその情報を発信しているのか」という点に他なりません。特に、BtoB企業の場合は権威性の有無がビジネスの成功に直結するため、企業としての実績や専門家の関与を明確にすることがポイントです。
例えば、コンテンツを作成する際に専門的な知識を持つ人物に直接取材したり、記事の監修を依頼したりすることで、その権威性を高めて、AIに「この情報を参照すべきだ」と判断させる要素となります。また、企業の代表者や担当者のプロフィール、実績を記事に明記することも、権威性の向上に繋がります。
Trustworthiness(信頼性)を担保するために「透明性」を確保する
どんなに素晴らしい一次情報でも、その情報源が不明確であればユーザーは安心して情報を利用できません。情報の信頼性を高めるための透明性は、AIに引用されるためにも不可欠です。権威性とも関連しますが、ここで重要視されているのは、情報を検証可能な形にすることです。
他のデータを引用する場合は、政府や公的機関、リサーチ会社など、信頼性の高い一次情報を引用し、出典を必ず明記しましょう。また、自社の調査データを用いる場合も、調査時期や対象などの調査概要を明確にすることで、コンテンツ全体の信頼性が向上します。
その2:AIに「引用される」コンテンツ構造を意識する

AI Overviewsに引用されることは、「その1」で解説したE-E-A-Tの高いコンテンツをAIが「信頼できる情報源」として評価した証であり、新しい形のブランド認知と捉えることができます。たとえ直接のアクセス(クリック)に繋がらなくても、AIの回答にあなたのWEBサイトが引用元として表示されることは、権威性を高める上で非常に有益です。
そこで重要になるのが、コンテンツの構造です。せっかく質の高い一次情報(E-E-A-T)を用意しても、AIがそれを迅速かつ正確に読み取れなければ引用のチャンスを逃してしまいます。では、AIに「これは使える情報だ」と判断してもらい、引用されやすくするためには、どのような構造にすれば良いのでしょうか?
その答えは、検索エンジンの最適化(SEO)から一歩進んだ「AEO(Answer Engine Optimization)」という新しい考え方にあります。端的に言えば、AIは人間が理解しやすいように論理的に整理された情報を好みます。このAIの特性を理解することで、目指すべきコンテンツの構造はおのずと明らかになるでしょう。
簡潔なQ&A形式で「明確な答え」を冒頭に示す
AI Overviewsは、ユーザーの質問に対して明確な「答え」を返すことを目的としています。そのため、コンテンツの冒頭や重要なセクションで、ユーザーが検索しそうな質問に対する簡潔な回答を提示する構造が非常に効果的です。
例えば、WEBサイト制作に関する様々な疑問に答えるコンテンツを作成すると仮定します。この場合、「WEBサイト制作の費用相場は?」というようなユーザーの質問を想定して、簡潔に回答することが重要です。こうした、多くの人が抱えていそうな疑問を記事のタイトルや中見出しに設定した上で、その直後に「中小企業の場合、機能によって300万円〜500万円が相場です」といった結論をすぐに提示する構造にしましょう。詳細な説明はその後に続けます。
これは、より専門性の高い複雑なコンテンツの場合でも同様です。この「質問と回答のセット」を記事内で意識的に配置することで、AIが情報を瞬時に抽出しやすくなり、結果的に引用されやすくなります。
構造化データ(スキーママークアップ)で「コンテンツの意図」を伝える
構造化データ(スキーママークアップ)とは、コンテンツの内容を検索エンジンやAIに正確に理解させるための、「AIのための指示書」のようなものです。
これを設定すると、「この記事の重要な結論はここです」「これはよくある質問とその答えです」といった、情報の本質的な意味を機械に直接伝えることができます。
複雑な記述形式が裏側で使われていますが、大切なのはAIが正確に情報を処理できるように道筋を示すことです。
特に、以下のような形式が決まったコンテンツでは、構造化データの活用が不可欠です。
- よくある質問と回答(FAQ):記事の中で「Q&A」形式を使っている場合、AIがユーザーの質問に対して直接的に回答を引用しやすくなる
- 具体的な手順やハウツー:「〇〇する方法」といった手順をステップごとに解説している場合、AIが効率的に情報を引用できるようになる
AIに情報を選んでもらうには、データを構造化することにより、「私はこの質問に答えています」と明確に自己申告することが重要なのです。
箇条書きやリスト形式で「視覚的なわかりやすさ」を高める
繰り返しになりますが、AIは複雑な文章よりも、整理され、構造化された情報を好みます。AIは複数の情報源を参照して、重要な要素を抽出・統合して回答を作成するため、誤解をしやすい複雑な文章を敬遠する傾向があります。その反対に、誤認なく正確に処理しやすい箇条書きやリスト形式は好まれます。
箇条書きやリスト形式にセイルすることは、AIだけでなく、人間にとっても情報を理解しやすくするという大きなメリットがあります。特に、メリット・デメリットや手順、料金プランなど、比較・羅列する必要のある情報を示す際には積極的に箇条書きや表を活用しましょう。視覚的に整理されたコンテンツは、結果的に「読みやすい=質の高い」とAIにもユーザーにも評価されることに繋がります。
その3:Google検索だけに頼らずに集客チャネルを増やす
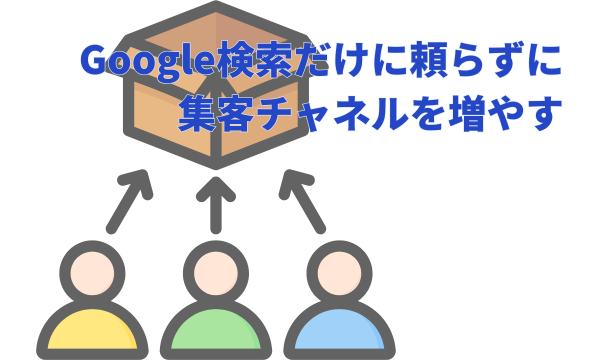
ここまで見てきた通り、GoogleのAI Overviewsに引用してもらうためにはいくつか重要なポイントがあります。これを押さえて、AIに評価されることができれば、サイトの訪問者数を増加させたり、自社のサービス・商品に関心のある潜在的顧客に効果的にリーチできる可能性があります。
一方で、従来の自然検索からのクリック率(CTR)は不安定になる可能性があります。また、競合もAIモードに最適化するために様々な施策を講じてくると考えられるため、「◯◯をすれば大丈夫」というようなAIモード必勝法は存在しない状況です。
そのような不安定性が高まる時代において、特定の集客チャネル、特にGoogle検索に流入を依存していると、今後のアルゴリズムの変更や新機能の導入、競合他社の動向によって、事業全体が大きな打撃を受けるリスクが高まります。
今のうちに「脱Google依存」を図り、複数の集客の柱をつくることが、事業を安定させる上で極めて重要になるのです。Google検索からの流入が減っても事業が揺るがないように、今のうちからWEBマーケティングのポートフォリオを多様化していくことが、WEBサイト運営の必須戦略となります。
指名検索(ブランド検索)を戦略的に促進する
AIモードの影響を最も受けにくいのが、企業名やサービス名で直接検索される「指名検索」です。ユーザーが「この会社を調べたい」「このサービスについて知りたい」と明確な意図を持って検索するため、検索結果がAI Overviewsで要約されたとしても、あなたのWEBサイトにアクセスする確率は非常に高いまま維持されます。
安定した流入を確保するためには、SNSでの情報発信、専門的なWEBセミナーの開催、プレスリリース、業界イベントへの出展などを通じて、ブランド自体の認知度を高める施策を強化しましょう。ユーザーに「〇〇という会社名で検索しよう」「このテーマなら〇〇のブログで読もう」と思ってもらうこと。これが、AI時代における最も強力で安定した流入源となります。
コンテンツを多角展開し「脱Google依存」チャネルを築く
「Google依存」の状態とは、苦労して制作した質の高いブログ記事などを閲覧してもらえるかどうかが、Google検索の結果次第ということを意味します。一つしかユーザーとの接点がないことは非常にもったいない状況です。AI時代の安定運営の鍵は、コンテンツを様々な形で再利用し、複数のチャネルでユーザーとの接点を持つことです。
例えば、ブログ記事の内容を切り出して、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで発信することで、普段Google検索を使わない層とも接点を持てます。さらに、ブログの内容を掘り下げてYouTubeで動画コンテンツとして解説すれば、より深いエンゲージメントを生むことも可能でしょう。
また、メールマガジンは、Googleのアルゴリズムに一切左右されない、読者に直接情報を届けられる強力なチャネルです。これらのチャネルでファンを育成し、直接WEBサイトへ誘導できる関係性を構築しておくことが、将来の安定したメディア運営の鍵となります。
その4:企業ブログの成果を測るための新しいKPIを設定する

AIモードの登場により、従来のWEBマーケティングの「当たり前」だった考え方をアップデートする必要があります。トラフィックの減少が予想される中で、オウンドメディアの成果をクリック数やアクセス数といった指標だけで測ることは、ブログの真の価値を見誤ることに繋がります。
今、私たちが注目すべきは、「ブランドへの貢献」や「エンゲージメントの質」といった、より本質的な指標です。従来のSEO指標から脱却し、企業ブログの価値を多角的に評価するための新しいKPIを設定しましょう。
新しいKPIを導入することで、ブログの真の価値を多角的に評価し、次のコンテンツ戦略を立てることができるようになります。AI時代は、「どれだけ多くの人に見てもらったか」から「どれだけ深く信頼されたか」へと、成果の定義そのものが変わりつつあるのです。
AIによる概要への「引用・言及数」を追跡する
AI Overviewsに自社サイトが参照元として表示されることは、新しい形のブランド認知と捉えるべきです。たとえクリック数がゼロでも、GoogleのAIがあなたのコンテンツを「信頼できる情報源」として選んだという事実は、その分野におけるブランドの権威性を高めてくれます。
今後は、Google Search Consoleなどのツールで、AI Overviewsからのトラフィックだけでなく、「AIの回答内で自社サイトが参照元として表示された回数」を定期的に追跡することが重要になります。これは、コンテンツのE-E-A-TがGoogleに正しく評価されているかを確認する、重要なバロメーターとなります。
「ブランド名での検索回数」を認知度向上の証拠とする
AIモードの影響を最も受けない「指名検索」の回数をKPIに設定しましょう。ブログ記事やSNS、その他のマーケティング活動が、最終的にどれだけユーザーに自社の「ブランドを覚えてもらい、検索行動にまで繋げられたか」を測ることができます。
指名検索数が増加しているということは、従来のアクセス数といった指標が増えていなくても、コンテンツがユーザーの記憶に残り、ブランドの認知度向上に貢献している動かぬ証拠です。この指標を追うことで、ブログがリード獲得の「入口」としてだけでなく、ブランド構築の「基盤」としても機能しているかを評価できるようになります。
Google検索以外での「共感・行動の指標」を重視する
Google検索からの流入が減ったとしても、読者がコンテンツに共感し、行動に移してくれるのであれば、それは企業の財産となります。そこで、「脱Google依存」の指標として、SNSでのシェア数やメールマガジン登録者数などのエンゲージメント指標に注目しましょう。
コンテンツがSNSで活発にシェアされているということは、読者が「この情報は価値がある」と認め、他者にも広めたいと感じている証拠です。また、メールマガジンへの登録は、ユーザーが「継続的に情報を得たい」という強い意思を示しているため、将来のリード顧客として最も質の高い行動の一つです。これらの指標を追うことで、ブログの真のファンがどれだけ育成できているかを測ることができます。
まとめ:AI時代は「本質」が問われるチャンス
AIモードの登場は、WEBマーケティングのルールを大きく変えるものですが、「ユーザーに役立つ、信頼できる情報を提供する」という本質は変わりません。むしろ、質の低いコンテンツはAIによって淘汰され、本当に価値のあるコンテンツだけが評価される時代が来る、と捉えるべきでしょう。
この変化を脅威と捉えるだけでなく、自社の専門性を発揮し、ブランド価値を高める新たな機会と捉え、戦略的に対応していくことが求められます。
株式会社MUでは、企業の強みを活かしたDX戦略立案から、最新のトレンドを捉えたWEBサイト制作、WEBマーケティング支援まで、お客様のビジネス成長をトータルでサポートしています。
「AIモードの登場で、今後のWEBサイト運営に不安がある」
「ブログのリニューアルを検討している」
このようなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。お客様の課題に真摯に向き合い、最適な解決策をご提案させていただきます。