release:
「このデザインは完璧!」
そう思って公開したWEBサイトや、自信を持ってリリースしたサービスロゴ。それがまさか、知らず知らずのうちに法律に触れてしまい、突然訴えられてしまうなんて……。
そんな恐ろしい事態、他人事だと思っていませんか?
実は、デザインに関する法律は複雑で、一般的な「このくらいは大丈夫だろう」という感覚が通用しないことも少なくありません。そのため、知らない間に法的な落とし穴にはまってしまい、大切なビジネスが訴訟トラブルに巻き込まれるケースは、決して少なくありません。
あなたの会社やブランドを守るためにも、デザインに関わる法律の基礎知識は、ぜひ知っておきたいですよね。この記事で、そのポイントをわかりやすく解説していきます。
目次
作った人の権利を守るデザインの著作権

デザインを制作すると、そのデザインには「著作権」という権利が自動的に発生します。
著作権とは、周知の通り、作った人の権利を守るための法律です。言うまでもなく、あなたが作ったロゴやイラストを、誰かが無断で使用したり、コピーしたりすることは法律で禁止されています。この法律があることで、あなたや会社が作り上げたロゴやイラストなどの権利が保護されているわけですが、同時に無意識のうちに他者の権利を侵害してしまうリスクも発生しているのです。
どこまでならOK?
著作権は、デザインの「アイデア」そのものではなく、そのアイデアを具体的に表現した「形」を保護します。
そのため、他者のデザインからインスピレーションを得て、全く新しい表現として昇華させることは問題ありません。ですが、いくら自分の手でゼロから制作したとしても、「ほとんど同じデザイン」はNGです。
既存のデザインのフォントや色を変えただけでは、著作権侵害になる可能性が高いでしょう。このように作り手が明らかに模倣したケースが権利侵害に問われるのは当然のことです。
一方で、イラストやロゴが偶然似てしまう可能性も否定できません。そこで問題になってくるのが、どのくらい似ていれば(類似性があれば)著作権侵害になるか?という部分です。この点については、「本質的な特徴が共通しているか?」が判断基準になります。
あるデザインにおいて、「本質的な特徴はどこか」という線引きを明確にすることは容易ではないため、インスピレーションを受けたデザインと、「似ている」と判断される可能性がある段階で、著作権侵害となってしまうリスクがあると考えておきましょう。
著作権侵害は、損害賠償請求や刑事告訴の対象となる可能性があります。最悪の場合、裁判で多額の賠償金を支払うことになるかもしれません。
商標権と意匠権:ブランドを守るための盾
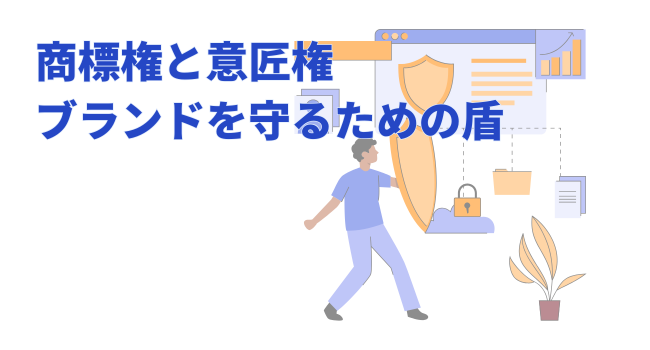
WEBサイトをデザインする際、著作権侵害に注意することはもちろんですが、商標権と意匠権についても理解しておく必要があります。これらは、著作権とは異なる役割を持つ、ビジネスを円滑に進める上で欠かせない法律です。
前章で解説した通り、著作権はデザインのアイデアそのものではなく、そのアイデアを具体的に表現した「形」、つまり作品を保護します。例えば、あなたが描いたイラストや書いた文章そのものに、作った時点で自動的に発生する権利です。一方、商標権と意匠権は、企業活動における「見た目」や「ブランド」を守るための権利であり、特許庁への登録が必要となります。
商標権:サイト名やロゴは大丈夫?
もし、あなたが丹精込めて作った会社のロゴやサービス名が、突然、全く別の企業に無断で使われていたらどう感じるでしょうか?大切に育ててきたブランドが、他社によって利用されるのは避けたいですよね。
この「ブランドを守る」ための権利が商標権です。商標権は、商品やサービスを他のものと区別するための「マーク」や「ネーミング」を保護します。たとえば、ある企業のロゴやサービス名が商標登録されていれば、他社はそのロゴやサービス名を無断で使用できません。
WEBサイト名やロゴを考える際は、すでに他社が商標登録していないか、必ず確認するようにしましょう。特許情報プラットフォームなどのデータベースで簡単に検索できます。もし、すでに登録済みのものと酷似した名前やロゴをあなたが使用してしまうと、商標権侵害になる可能性があります。
意匠権:デザインの模倣はNG!
他社のWEBサイトのデザインを参考にすることは、アイデアの源として非常に有効です。しかし、そこからそっくりそのままコピーしたり、少し手を加えただけで酷似したデザインを使用したりすると、意匠権侵害になる可能性があります。
意匠権は、製品の「見た目」を保護する権利です。具体的には、製品の外観や形状、WEBサイトやアプリのUIなど、独自性のあるデザインが保護対象となります。WEBサイトで意匠登録される例としては、特定のレイアウト、アイコンのデザイン、ボタンの形状などが挙げられます。
つまり、著作権が「作品としてのデザインの形」を保護するのに対し、意匠権は「製品としての機能や見た目を高めるためのデザイン」を保護する役割があるのです
権利侵害を防ぐために
WEBサイトのデザインを始める前に、商標権と意匠権のデータベースを確認しましょう。不安な場合は、専門家(弁護士や弁理士)に相談することをおすすめします。
商標権と意匠権は、企業のブランドや商品を保護するための重要な権利です。WEBサイトをデザインする際は、これらの権利を尊重し、トラブルのないように注意してください。
写真(特に人物)について

WEBサイトで使用する写真は、著作権や肖像権など、様々な権利に関わってきます。これらの権利を侵害すると、訴訟トラブルに発展する可能性もあるため、十分な注意が必要です。
肖像権の落とし穴
人物写真を使用する場合に、特に注意が必要なのが肖像権です。肖像権とは、自分の容姿を無断で撮影されたり、公開されたりしないように守るための権利です。たとえ写真の著作権をクリアしていても、写っている人物の肖像権を侵害する可能性があります。
例えば、イベントで撮影した集合写真をWebサイトに掲載する際、写っている全員から許可を得なければ、肖像権の侵害になるリスクがあります。
肖像権トラブルを避けるための対策
写真素材はWEBサイトの印象を大きく左右しますが、安易な使用は大きなリスクを伴います。トラブルを避けるためにも、写真を使用する際は、必ず権利関係を確認するようにしましょう。肖像権のトラブルを未然に防ぐには、以下の3つの方法が有効です。
著作権フリー素材サイトを利用する
WEBサイトに掲載する写真を自前で用意するのが難しい場合、著作権フリーの写真素材サイトを利用するのが最も手軽な方法です。しかし、無料で使えるからといって、無条件で何にでも使えるわけではありません。各サイトごとに利用規約が異なるため、使用前に必ず下記のようなポイントを確認しましょう。
- 利用範囲(商用利用の可否、加工の可否など):商用利用が許可されているか、トリミングや色調補正などの加工はどこまで許されるのか
- クレジット表記の必要性:写真の出典元を明記する必要があるか
- 禁止事項:アダルトサイトでの使用禁止など、特定の用途が禁止されていないか
たとえフリー素材であっても、提供元が定めた規約に違反すれば、権利問題に発展する危険性があるため、十分な注意が必要です。
モデルリリース(肖像使用許諾契約)を取得する
最も安全なのは、写真の被写体からモデルリリースと呼ばれる書面での同意を得ることです。モデルリリースには、写真の使用目的や使用期間、範囲などが明記されており、被写体の許可を得た上で安心して写真を使用できます。
個人が特定できる写真の取り扱い
学校の集合写真やイベントの写真など、個人が特定できる写真をWEBサイトに掲載する場合は、特に慎重な対応が求められます。必ず写っている関係者全員から、書面での許可を得てから使用するようにしてください。
他のサイトからの引用等について
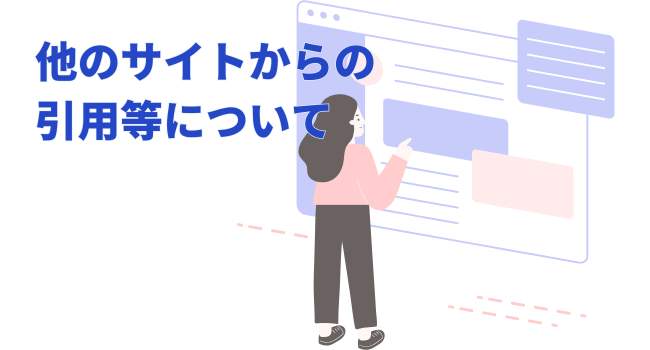
他のサイトから情報を引用等をする場合は、著作権法上の引用ルールを守る必要があります。
引用の条件
- 引用元を明記する(サイト名、URL、著者名など)
- 引用部分を「」などで囲むなど、明確に区分する
- 引用部分が従となり、引用する側のコンテンツが主となるようにする。
- 必要最小限の範囲で引用する
引用・参考・出典の違いと表記ルール
- 引用:他者の著作物の一部を、自分の著作物の中で「そのまま(原文のまま)」使用する場合を指す。必ず引用元を明記し、「」などで囲んで引用部分を明確にしなければならない
- 参考:他者の著作物から情報を得て、自分の著作物を作成する場合に該当する。引用ほど直接的なものではないが、参考にした文献やサイトを明記することが望ましい
- 出典:情報の出所や根拠を示す場合。引用元や参考元よりも広く、主に画像や図表などに使用する
【予防策】トラブルを避けるためにできること

デザインに関する法律は、一見難しそうに感じるかもしれません。しかし、ポイントを押さえれば、あなたのビジネスを力強く守る盾になってくれます。事前にしっかりと対策を講じることで、ほとんどの場合トラブルは回避できるのです。ここでは、その具体的な対策例を紹介します。
権利関係の確認
デザインを使用する前に、必ず権利関係を確認しましょう。
特に、インターネット上で見つけた画像やイラストを使用する場合は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)が付いているかなど、著作権フリーであるかを確認することが重要です。
有料素材サイトを利用する場合でも、利用規約をよく読み、使用範囲を確認しましょう。
また、他社のロゴやデザインを参考にしたい場合は、それが権利侵害にならないか、特に注意が必要です。少しでも不安な場合は、次の「専門家への相談」も検討してみてくださいね。
専門家への相談
デザインの権利関係について「これで大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、弁護士や弁理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法律的な知識はもちろん、実際のトラブル事例にも精通しています。早い段階で相談することで、思わぬトラブルを未然に防ぎ、安心してデザインを使用できますよ。
- 弁護士:著作権、商標権、意匠権に関するトラブル全般に対応
- 弁理士:商標登録や意匠登録の申請、権利侵害に関する相談に対応
まとめ:デザインの法律、知っておいて損はない!
デザインに関する法律は、難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な知識を知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
デザインを安心して利用するために、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
株式会社MUでは、デザイン制作における法務体制も万全です。お客様が安心してデザインをご利用いただけるよう、権利関係の確認や契約書の作成、写真素材の選定、引用ルールの遵守などもサポートいたします。
WEBデザインのことでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。








